



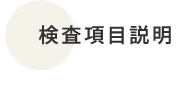
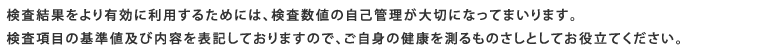
表は横にスクロールすることができます。
| 検査項目 | 正常値範囲 | 内容 | ||
| 下限値 | 上限値 | |||
| 白血球数 | 4 | 9 | 身体の中に炎症があると高値を示します。 | |
| 末梢血液像 | 顆粒球 43.0~76.0% 単球 4.0~10.0% リンパ球 17.0~48.0% |
赤血球や白血球の形態や、白血球の種類別の割合を調べる検査です。 | ||
| 赤血球数 | 4.2 | 5.5 | 赤血球数を調べ、貧血などを調べます。 | |
| 血色素量 | 11.3 | 15.5 | 酸素を運搬する働きをします。貧血を調べます。 | |
| ヘマトクリット | 36 | 54 | 血液中の血球成分の%を示しています。 | |
| 血小板 | 130 | 369 | 止血の為に働く血球で、減少すると出血しやすくなります。 肝機能障害で減少することがあります。 |
|
| 総たんぱく | 6.7 | 8.3 | 血液中の蛋白の量で栄養状態や腎障害、肝障害の指標となります。 | |
| たんぱく分画 | A1b 60.2~71.4 α1 1.9~3.2 α2 5.8~9.6 β 7.0~10.5 γ 10.6~20.5 A/G比 1.2~2.0 |
たんぱく成分の特徴的な変動をみるもので、 肝硬変や腎障害の指標となります。 |
||
| アルブミン | 4.0 | 5.0 | 肝臓で生成される蛋白質の一種で、日常の診断では一般状態の判断の指標となります。 | |
| 総ビリルビン | 0.3 | 1.2 | 黄疸の診断とともに代謝過程、病態経過などを把握することができます。 | |
| 直接ビリルビン | 0 | 0.4以下 | 肝炎、胆道疾患の診断経過観察、予後判定や黄疸の鑑別に有効です。 | |
| GOT | 10 | 40 | GOT、GPTは、肝臓に多く含まれる酵素で、組織に障害があると、血液中の値が上昇します。 これらが極端に高い値を示すと種々の血液中の値が上昇します。 これらが極端に高い値を示すと種々の肝障害が疑われます。 |
|
| GPT | 5 | 40 | ||
| LDH | 115 | 245 | 心筋や肝臓、骨格筋、赤血球等に多く含まれる酵素で、心筋障害や肝障害などが 起こると血液中の値が上昇します。 | |
| ALP | 115 | 359 | 骨や肝臓などに多く含まれる酵素で、これらの臓器の障害で高値を示します。胆のう、胆管の障害で上昇することがあります。 | |
| γ-GTP | M:70以下 F:30以下 |
肝臓などに分布する酵素で、胆汁うっ滞、アルコール、薬物などの影響で上昇します。肝炎、閉塞性黄疸、胆石などで胆汁うっ滞が 生じた場合に測定値は上昇し、特にアルコールに敏感に反応することがあるほか、鎮痛剤などの薬物でも上昇することがあります。 | ||
| CK | M:62 F:45 |
M:287 F:163 |
心疾患、筋疾患、脳の損傷状態を知ることができます。 激しい運動後の検査では高くなります。 |
|
| ZTT(クンケル) | 2.0 | 12.0 | 血清に試薬を加えて、血清が濁る程度によって肝臓の機能を調べます。 | |
| 中性脂肪 | 50 | 149 | 中性脂肪は、エネルギー源として利用されますが、過剰となれば皮下や肝臓に蓄積して、肥満や脂肪肝の原因となります。 また、動脈硬化も促進されます。 |
|
| 総コレステロール | 150 | 219 | 各種脂質代謝の異常の解明や動脈硬化の危険性の予知に有効です。 | |
| HDLコレステ(善) | 40 | M:86 F:96 |
俗に善玉コレステロールとよばれるもので、 このHD Lコレステロールが十分あると動脈硬化が抑えられます。 |
|
| LDLコレステ(悪) | 70 | 139 | 俗に悪玉コレステロールとよばれるもので、高値の場合は動脈硬化の原因となります。 | |
| 尿酸 | M:3.7 F:2.5 |
7.0 | 代謝異常により濃度が高くなると、関節にたまり、痛風の原因になります。 | |
| 尿素窒素(BUN) | 8 | 22 | BUNも老廃物の一つでクレアチニンとほぼ同じ意味を持ちます。 | |
| クレアチニン | M:0.6 F:0.47 |
M:1.0 F:0.79 |
クレアチニンは尿に排泄される老廃物ですが、 腎臓の機能が低下してくると血中に多く出てきます。 |
|
| アミラーゼ | 37 | 125 | すい臓から出るものと唾液腺から出るものがあり、どちらの病気でも血液中に増加してきます。 | |
| カルシウム(Ca) | 8.5 | 10.2 | 副甲状腺疾患、骨疾患、腎疾患などで異常値となります。 | |
| ナトリウム(Na) | 136 | 147 | 体内の水分とミネラルのバランスが崩れた時に異常値になります。 | |
| カリウム(K) | 3.6 | 5.0 | 同上 | |
| 無機リン(P) | 2.4 | 4.3 | 甲状腺及び副甲状腺の異常、腎不全などがわかります。 | |
| グルコース(血糖) | 70 | 109 | 糖尿病の診断や経過観察の指標になります。食事の影響を受けます。 | |
| HbA1c | 4.3 | 5.8 | 過去1~3ヶ月前の血糖値の状態を推測できます。 | |
| 血清鉄 | M:54 F:48 |
M:200 F:154 |
ヘモグロビン合成に使用されます。貧血性疾患の鑑別診断上に重要な意義があります。 | |
| CA15-3 | 25.0以下 | 乳がんに特異性が比較的高く、主に乳がんの治療効果の判定や経過観察に用いられています。 | ||
| CA125 | 35.0以下 | 卵巣がんで高値になりやすく、その他子宮体がんや、すい臓、胃、大腸などのがんで高値になることがあります。 子宮内膜症、月経、妊娠、肝硬変、膵炎などでも上昇します。 |
||
| CA19-9 | 37.0以下 | すい臓がんをはじめ、胆道、胃、大腸のがんなど、主に消化器のがんで高値になります。 | ||
| CA72-4 | 4.0以下 | 卵巣がんの他、乳がん、胃がん、大腸がんでも高値になります。 子宮内膜症でも高値になります。 |
||
| NCC-ST439 | 7.0以下 | 乳がんや肺、胃がんなどで高値になります。 | ||
| SCC | 1.5以下 | 主に、肺や食道、子宮頚部の扁平上皮がんで高値になります。 皮膚の病気で増加することもあります。 |
||
| STN | 45以下 | 卵巣癌全体では陽性率が低いものの、粘液性嚢胞腺癌では高値を示します。 | ||
| PSA | 4.0以下 | 前立腺に特異性の高い腫瘍マーカーで、がんの発見や経過観察に重要な役割を果たしています。 前立腺炎や前立腺肥大で上昇することもあります。 |
||
| DUPAN-2 | 150U以下 | 胆管がん(胆管癌)や胆嚢がん・すい臓がん・肝臓がんなどで高い陽性率を示す一方で食道がんや胃がん、大腸がんなどの消化器がんでは陽性率が低いという特徴があります。 | ||
| エスタラーゼ | 100~400 | エラスターゼはタンパク分解酵素の一種で、すい臓以外に白血球、血小板、大動脈などに存在しますが、すい臓に含まれる量が最も多く、すい臓がんが疑われる場合に測定されます。 | ||
| CEA | 5.0以下 | 大腸がんなどの消化器のがんをはじめ、肺、卵巣、乳がんなどで高値になります。喫煙や炎症性疾患、肝硬変、 糖尿病で高値になることもあります。 | ||
| CYFRA | 3.5以下 | 扁平上皮がんで高値になり、主に肺の扁平上皮がんや頭頚部腫瘍の経過観察に用いられます。 | ||
| ProGRP | 70未満 | 肺の小細胞がんで高値になりやすく、治療効果の判定や経過観察などに用いられます。 | ||
| NSE | 10.0以下 | 神経組織や神経内分泌細胞に特異的に存在する物質で、肺の小細胞がんや神経芽細胞腫などで高値になります。 | ||
| AFP | 10.0以下 | 臓器特異性の高い腫瘍マーカーで、肝がん、卵巣や精巣の胚細胞がんで高値になります。まれにAFPが高くなる胃がんもあります。 慢性肝炎や肝硬変、妊娠などでも値が上昇します。 | ||
| PIVKA-II | 40.0未満 | 臓器特異性の高い腫瘍マーカーで、肝臓がんで高値になります。肝臓がんの発見や経過観察にAFPと併用されます。 | ||